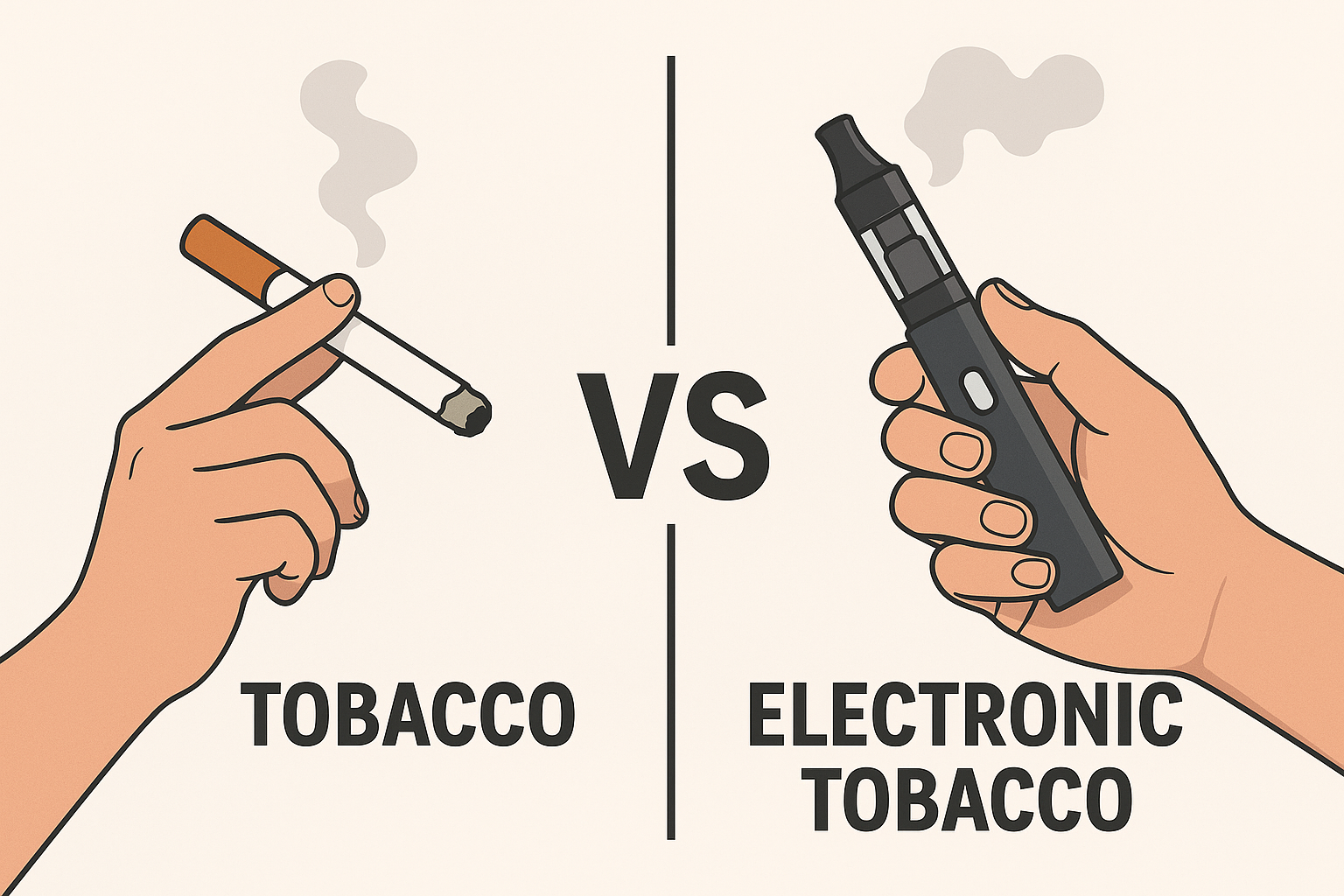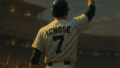夕暮れが街の輪郭を曖昧にしはじめた頃、山本慎一はようやく仕事用のノートパソコンを閉じた。
数字と文字に支配された一日が終わる瞬間、肩に背負っていた見えない重しが外れていく感覚がした。
キッチンに立つと、冷蔵庫のモーター音が静かに部屋の空気を震わせている。
「今日は……何にしようか」
慎一はそう呟きながら、冷蔵庫を開けた。
残業帰りの夜は、いつもより晩酌に力が入る。自分を労うためのささやかな儀式。
冷蔵庫には昨日の残り物の煮物、買い置きの枝豆、小皿に盛れば充分“晩酌の友”になる食材が控えていた。
それでも彼の目にまず飛び込んできたのは、一升瓶の横にひっそりと佇む小さな四合瓶だった。
「飛騨の生酒……そういえば先月の出張帰りに買ったんだったな」
淡い青の瓶からは、山に積もる雪のような冷気が伝わる気がする。
今日はこれで決まりだった。
小さな鍋に湯を沸かし、枝豆を入れた。
塩は少し多め。枝豆の香りが湯気とともに立ちのぼると、慎一の肩の力がすっと抜けていく。
「この匂い、夏の記憶だな……」
子どもの頃、縁側で祖父とともに麦茶を飲みながら食べた枝豆。
外は蝉が狂ったように鳴いていて、汗が流れても気にしないほど無邪気だったあの時間。
大人になった今、あの頃のような時間は戻らない。
だけど、晩酌というささやかな儀式は、思い出の扉をそっと叩く。
鍋の火を止めると、慎一はふぅっと息を吐いた。
仕事の疲れも、人間関係の難しさも、家の中ではひとまず忘れていい。
そんな気分になれるのが、晩酌の不思議な力だった。
リビングの照明は抑えめにし、間接照明だけをつける。
その柔らかな光は、部屋をまるで別の世界に変える。
静かで、落ち着いていて、他の何も必要としない空間。
テーブルに生酒の瓶を置き、ぐい呑みを手に取った。
お気に入りの陶芸家の作品。
釉薬の揺らぎが美しく、光の角度で表情が変わる。
日中の世界では役に立たないが、夜の世界では主役になれる器。
慎一はその器に、ゆっくりと酒を注ぐ。
トクトク……。
線の細い音が、静寂の中に溶けていく。
一口目を口に含んだ瞬間、冷たさとともに甘みが広がり、後からふわりと米の香りが追いかけてくる。
「ああ……これはいい」
たった一杯の酒が、こんなにも心を解きほぐすのかといつも思う。
枝豆のひと粒を口に運べば、塩気と酒が交互に舌を刺激し、また杯を進めたくなる。
テレビもスマホもつけていない。
耳に入るのは、外を走る車の遠い音と、冷蔵庫のかすかな振動だけ。
都会の夜は静寂とは無縁のようでいて、こうして家にいると、音が全部遠くに感じられる。
まるで自分だけが時間の外側にいるような感覚。
二杯目を注いだ頃、慎一はベランダに出た。
夜風が頬を撫で、仕事で熱を持った頭を冷やしてくれる。
マンションの下を見下ろせば、街灯の下で犬を散歩させている人がぽつり。
その少し先では、コンビニの明かりがいつもと同じように灯っている。
「みんなそれぞれの夜を生きてるんだよな」
そう思うと、少しだけ胸が温かくなる。
ベランダの手すりにぐい呑みを置き、夜空を見上げる。
ビルの隙間から小さく星が瞬いていた。
都会の夜でも、星が見えると妙に嬉しい。
まるで“今日もお疲れさま”と誰かに言われたような気分になる。
慎一の胸に、ふとある人の顔が浮かんだ。
かつて恋人だった女性、佐伯美咲。
笑うと目尻に小さなしわが寄る、柔らかい表情の人だった。
別れてから半年が経つ。
きっかけは小さな行き違いだったが、積み重なった苛立ちや不器用さが二人を離れ離れにした。
「もう少しうまくやれなかったのかな」
晩酌をしていると、ときどきそんなことを思い出す。
だけど、酒の力は心を乱すのではなく、そっと撫でる。
後悔は、思い出の輪郭を曖昧にしてくれる。
美しい記憶だけを残して。
「元気でやってるといいな」
夜風に溶けるように呟いた。
部屋に戻ると、酒の酔いがほどよく身体を包み、空気まで柔らかく感じる。
三杯目を注ぐ前に、慎一は冷蔵庫からもう一品を取り出した。
鶏の山椒焼き。
スーパーで買ったものだが、温めるだけで香りが立ち、酒のつまみには充分だ。
食事をつつきながらの晩酌は、ただの“飲酒”とは違う。
仕事のこと、人間関係のこと、これからのこと。
普段は心の奥に押し込んでいる考えが、酒によってゆっくりと浮かび上がる。
考えるというより、眺める。
自分の人生を横から見ているような、不思議な距離感。
「明日は少し早起きして、散歩でもするか」
普段なら思いもしないことがふと頭に浮かぶのも、晩酌の魔法のひとつだ。
時計を見ると、すでに22時を過ぎていた。
酒はまだ半分ほど残っているが、今夜はこのあたりで切り上げるつもりだった。
酔いが深まりすぎると、せっかくの“静かな夜”が崩れてしまう。
慎一はぐい呑みを洗い、布巾で丁寧に拭いた。
毎日使うわけではないが、晩酌のたびに大切に扱う。
それが、自分を整える時間を大切にするという行為でもある。
部屋の照明を落とし、寝室の扉を開ける前に、慎一はもう一度だけリビングを振り返った。
温かい灯り、食器の匂い、ほんのり残る酒の香り。
そこには、今日を生きた自分の痕跡が静かに存在していた。
「よし。明日もなんとかなる」
晩酌の締めくくりに、彼は小さく笑った。
このささやかな儀式こそが、彼にとって“今日を終えるための鍵”であり、
“明日をはじめるための橋”でもあった。
静かな夜は、ゆっくりと深まっていく。
そしてその静けさは、明日の慎一にそっと寄り添うために、
今日という日の最後のページを優しく閉じたのだった。
翌朝、慎一は珍しくアラームが鳴る前に目を覚ました。
窓の外は淡い朝日が滲み、昨夜の酒の香りはすでに部屋から消えている。
その代わり、どこか胸の奥に、静かな温もりだけが残っていた。
キッチンでコーヒーを淹れながら、彼はふと昨日考えたことを思い出した。
「早起きして散歩でもするか」
あのときは酔いのせいだと思ったが、今朝は不思議と身体が軽い。
なんとなく、行けそうな気がした。
外に出ると、朝の空気はひんやりしていて、頬を刺すような冷たさが心地いい。
通勤前の人々が静かに駅へと歩き、パン屋の前には焼きたての香りが漂っていた。
慎一は深呼吸しながら、昨夜とは違う街の表情を楽しむ。
人々の歩く音、朝の車のエンジン音、新聞配達の自転車のきしみ。
どれもが“新しい一日の始まり”を告げていた。
(昨日の自分とは、ほんの少しだけ違う気がするな……)
そう思いながら歩くうちに、慎一はあることに気づいた。
昨日の晩酌は、ただ酒を飲んだだけではなかったのだ。
自分の中で絡まっていた思いをほどき、
心を静かに整理するための時間だった。
美咲のことも、仕事の疲れも、未来への不安も。
すべてが昨夜の静けさの中で、少しだけ形を変えていた。
「よし」
彼は小さく呟いた。
今日という一日は、昨日より少しだけ良いものになる。
そんな予感があった。
マンションに戻る頃、朝日が完全に顔を出し、空は柔らかい黄金色に染まりはじめた。
部屋に入った慎一は、ふとテーブルに残された昨夜の晩酌セットを見た。
きちんと拭かれたぐい呑み、生酒の瓶は冷蔵庫の中で静かに眠っている。
その光景を眺めながら、慎一は微笑んだ。
晩酌とは、今日を終わらせるための儀式であり、
同時に、明日を始めるための心の準備でもあるのだと。
ゆっくりと、確かに、日々は続いていく。
昨夜の灯りの下で感じたあの静けさが、
新しい一日の背中をそっと押してくれる。
慎一はコートを羽織り、玄関の扉を開けた。
「――行ってきます」
その声は、誰に届くわけでもなく、
それでも確かに“今日の自分”に向けて放たれたものだった。
そして彼は、昨日より少しだけ澄んだ足取りで仕事へ向かっていった。
静かで、確かな朝が始まっていた。