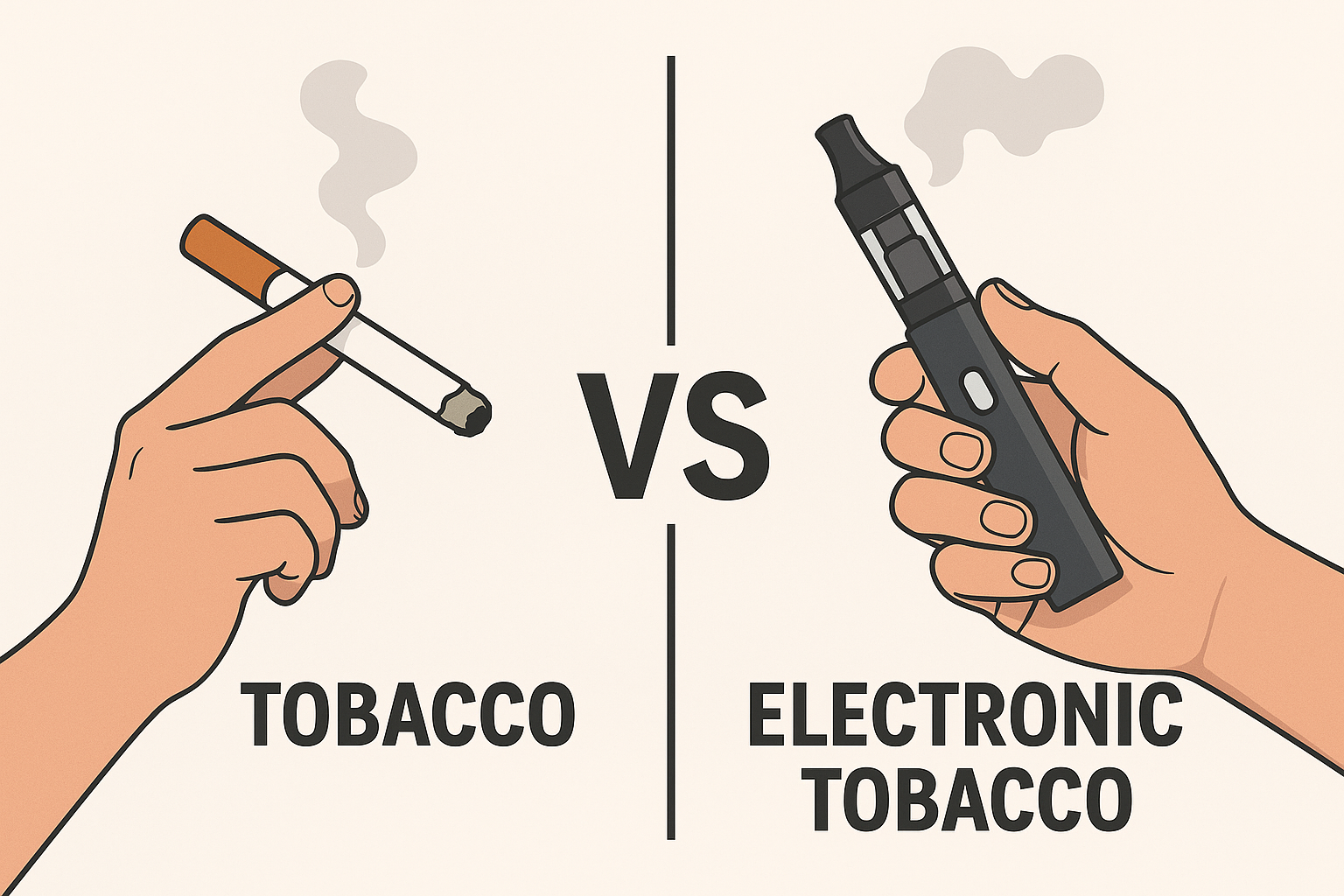一年のうちで、もっとも静かで、もっとも深く記憶に残る季節がある。
冬。
空気は冷たく、景色は淡い色合いに染まり、世界が一度立ち止まったように感じられる季節。
物語はその始まりを告げる、十二月初めの夕暮れから始まる。
■第一章 白い息と、最初の風
「今年も、冬が来たね」
凛はマフラーの端を指でくるくる巻きながら、白い息を空に溶かした。
商店街のアーケードには、早すぎるとも思えるイルミネーションが点灯し始めていた。青白い光が舗道を照らし、人々の影を細く長く伸ばす。どこからか流れてくるクリスマスソングが、季節の移り変わりを否応なく告げていた。
凛は毎年、この瞬間が好きだった。
寒さで指先がじんじんして、手袋を探して鞄をまさぐる癖。
冷たい外気を吸い込むと、胸の奥にまで冬が降りてくる感覚。
そして、それを温め返してくれるような、街の灯り。
「……凛!」
振り向くと、幼なじみの悠斗が小走りで駆け寄ってくる。
相変わらず少し大きめのコートを羽織り、鼻を赤くしながら。
「お待たせ。部活が思ったより長引いてさ」
「ううん、私も今来たところ」
これは、毎年の二人の合言葉だった。
悠斗は空を仰ぎ、小さく息を吐く。
「雪、降りそうだな」
「分かるの?」
「なんとなく、空気で分かる。凛は?」
「…分かんないけど、降ったら嬉しいな」
二人は肩を並べて歩き出した。
冬が始まる音を聞くように、まだ見ぬ雪の気配に耳を澄ませながら。
■第二章 こたつの灯りと、静かな夜
その日の夜、凛はこたつで丸くなっていた。
母が作ってくれたクリームシチューの香りが部屋に残っている。窓の外は完全な夜の色で、家々の煙突から白い湯気が上がり、冬がすっかり根付いたことを知らせていた。
「冬って、どうしてこんなに静かなんだろう…」
凛はこたつの縁に頬を乗せながら呟く。
スマホには悠斗から送られてきたメッセージが並んでいた。
《今日の空、やっぱり雪の匂いだったよ》
《降ったら外で会おうぜ。雪合戦な》
《こたつ入ると一生出られない》
思わず笑ってしまう。
このやりとりが毎年変わらず続いていることが、どこか冬の風物詩のように思えた。
こたつ、湯気、ストーブの赤い炎。
外から聞こえる風の音。
冬の夜はすべてがスローモーションで流れ、心の奥底にまで沁みてくる。
しばらくすると、ふと窓が白く曇った。
凛はカーテンを少しだけ開け、外を覗き込む。
「あ……」
最初の雪が、静かに舞っていた。
■第三章 降る雪、積もる想い
次の日。
学校に向かう道には薄く雪が積もっていた。
誰も踏んでいない真っ白な道を最初に歩くときの、あの小さな背徳感と喜びが、凛の胸をくすぐった。
「おーい、凛!」
悠斗が手を振っている。その足元には、すでに丸めかけの雪玉。
「やめて!朝から雪合戦はやめて!」
「ちょっと試し投げしただけだって」
「絶対狙ってたよね!?」
「冬の挨拶だよ」
凛は笑って駆け寄った。
二人はいつもより少し早く家を出て、雪の道をゆっくり歩いた。
凛は雪が好きだ。
でも、雪そのものよりも、雪の中で変わっていく人々の表情が好きだった。
笑い声が少し増える。
マフラーを巻き直す仕草が慎重になる。
白い息の向こうに、相手の顔が赤く染まる。
冬は、人の心を少しだけ素直にする。
■第四章 冬まつりと、灯りの川
十二月も終わりが近づいた頃、町では毎年恒例の冬まつりが開かれた。
広場には屋台が並び、甘酒の香りが漂う。
焚き火の周りには手をかざす人々が集まり、その中心には光のトンネルが作られていた。
凛と悠斗は、毎年この祭りに来ている。
「ほら、行くよ」
「待って、ゆっくり歩きたいの」
凛は光のトンネルに足を踏み入れる。
無数の光が頭上に揺らめき、星空が地上に降りたようだった。
悠斗がぽつりと呟く。
「この景色、凛は好きだよな」
「うん。毎年見ても飽きない」
「…来年も一緒に見ような」
その一言に、凛の足は一瞬止まった。
光に照らされた横顔に、胸が少しだけ熱くなる。
「うん、来年も」
言葉は自然とこぼれ落ちた。
冬の灯りは、人の心の奥に眠っている気持ちをほんの少し照らしてくれる。
■第五章 除夜の鐘と、新しい息
大晦日の夜。
凛は家族と年越しそばを食べ、温かいコートを羽織って外へ出た。
町の寺では除夜の鐘が鳴り始め、人々が静かに歩いている。
空は澄み切り、星が信じられないほど明るく瞬いていた。
坂の上で待っていると、悠斗が息を弾ませて駆けてくる。
「間に合った!」
「遅いよ、もう寒いんだから…!」
二人は肩を寄せ合いながら、鐘の音を聞いた。
ゴォォン……という深い響きが、冬の空気を震わせる。
「新しい年、どんな年になるかな」
凛が呟くと、悠斗は夜空を見上げた。
「分かんないけどさ。…冬は好きだよ」
「どうして?」
「凛と一緒に過ごしてる時間が、一番多い気がするから」
白い息が重なり合う。
冬の冷たい風が頬を刺すのに、胸の奥だけがふわりと温かい。
凛はゆっくり息を吸い込んだ。
そして、吐いた白い息の向こうで、確かに微笑んでいた。
■最終章 冬の風物詩は、記憶をつなぐ
冬が終わる頃、凛は思う。
こたつの温もりも、
初雪の驚きも、
イルミネーションのまぶしさも、
甘酒の湯気も、
夜空の星の瞬きも—
すべてが、誰かと過ごして初めて「冬の風物詩」になるのだと。
冬は冷たく、厳しい季節だ。
けれど同時に、人が誰かの温もりを求める季節でもある。
凛はそのことを胸の中で確かめるように、マフラーを巻き直した。
今年の冬も、きっと忘れない。
そして来年の冬もまた、特別な物語が生まれるだろう。
白い息の向こう側で待っている、あたたかな光のように。
◆結末 ― 白い息が消える前に
春の足音が近づくころ、雪は街の端から少しずつ姿を消し始めていた。
朝の風はもう痛いほど冷たくなく、凛はマフラーを薄手のものに変えていた。
ある放課後、凛と悠斗は二人で川沿いを歩いていた。
冬のあいだ何度も訪れた場所。
雪の積もっていた遊歩道はすっかり乾き、木々の枝先には小さな蕾がついている。
「冬、終わっちゃうね」
凛が言うと、悠斗は歩みを止め、ほんの少し息を吸った。
「なあ凛。冬さ、今年は……すごく短く感じた」
「え?」
「いや、たぶん……楽しかったからだと思う」
凛の胸がゆっくり熱くなる。
白い息ももう出なくなった空気の中で、悠斗は続けた。
「来年も一緒に冬を過ごそうな。
雪の日も、祭りの日も、こたつで寝落ちする日も。
できたら……いや、できなくてもいいけど……」
悠斗は言葉を詰まらせ、視線を落とす。
その様子があまりにも不器用で、凛は笑ってしまった。
冷たい冬の間、何度も感じた胸の熱さが一気に込み上げる。
「……悠斗」
凛はそっと彼の袖をつまんだ。
「来年じゃなくても。
今でも。
ずっと一緒にいたいよ」
悠斗は驚いたように目を見開き、それからゆっくり笑った。
冬よりもやわらかい、春の光を思わせる笑顔だった。
その瞬間、風が二人の間を通り抜ける。
凛の髪が揺れ、悠斗のマフラーの端がふわりと浮いた。
もう白い息は出ない。
けれど胸の奥に灯る温もりは、冬よりもずっと強かった。
冬の風物詩のひとつひとつが、
二人だけの思い出として積もっていく。
季節が変わっても、
冬が終わっても、
あの日の光も、雪の匂いも、
初雪の涙のような冷たさも、
凛と悠斗の間に永遠に降り積もっていく。
これから先、何度季節が巡っても、
二人の冬は終わらない。